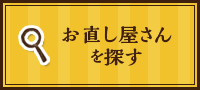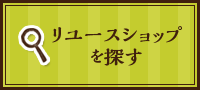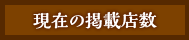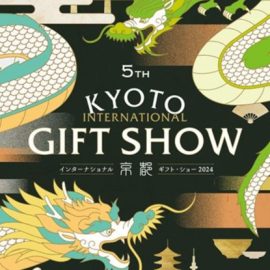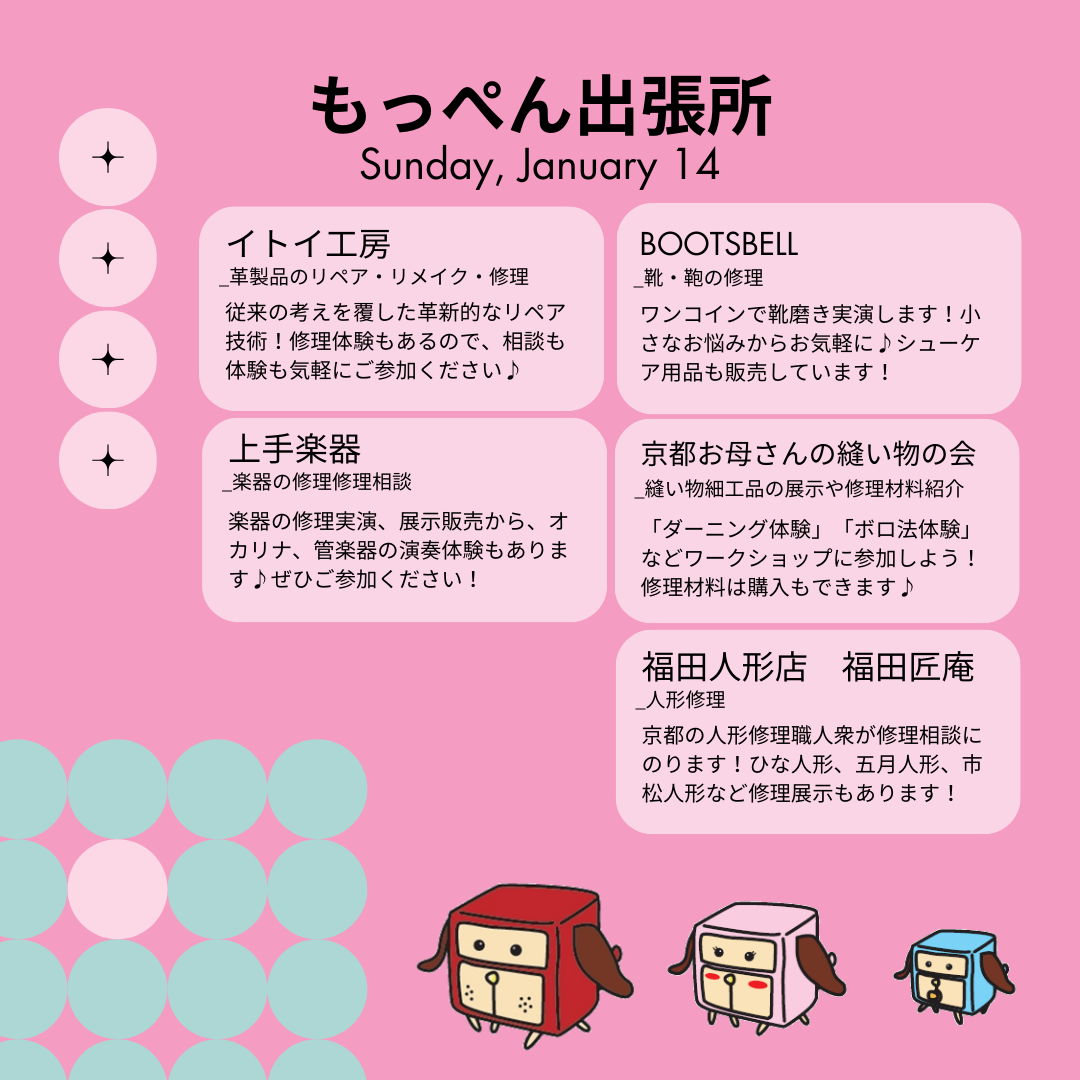京eco2Ring一覧
区ごとの一覧を見る
右京区 左京区 北区 上京区 中京区 下京区 西京区 東山区 山科区 南区 伏見区 その他地域
右京区
春日神社

阪急西院駅の少し北に位置するこの春日神社は、淳和天皇がこの地に移られる際に勅命により奈良の春日大社から分室を迎えられ、守護神とされたのにはじまりました。現在でも病気平癒や災難厄除の守護神として崇められ…(続きを読む)
妙心寺

臨済宗妙心寺派の本山で、1337年に花園法皇が自らの離宮を禅刹に改め、宗峰妙超が寺号を妙心寺と名づけ、美濃国から関山慧玄を開山として迎えたのが始まりです。その後一時衰退した後、細川勝元支援を受けて復興…(続きを読む)
木嶋神社(蚕の社)

この神社は「続日本紀」大宝元年(701)の条に神社名が記載されていることから、それ以前に祭祀されていたことがわかる古社です。この嵯峨野一帯は、古墳時代に朝鮮半島から渡来したすぐれた技術をもっていた秦氏…(続きを読む)
天龍寺

天龍寺の開基は足利尊氏で、暦応2(1339)年8月、後醍醐天皇が崩御した際、その菩提を弔うため、夢窓疎石が足利尊氏に進言し、光厳上皇の院宣を受けて開創されることになりました。観光名所の渡月橋や天龍寺北…(続きを読む)
広隆寺

京福太秦駅から歩いてすぐの所にある広隆寺は、真言宗御室派の寺院で、603年、帰化人系の氏族である秦(はた)氏の秦河勝(はたのかわかつ)が聖徳太子から授かった仏像を祀るために創建したものと言われています…(続きを読む)
西京極総合運動公園

阪急京都線西京極駅を下車約5分。昭和天皇御成婚奉祝記念事業として1942年に建設された運動公園。 その後、1988年の京都国体の主会場に決定したのをきっかけに、全面改修され、新たに総合運動公園として…(続きを読む)
広沢池

北嵯峨の昔ながらの風景は心なごむものがあります。 広沢池は北嵯峨の中でも、古来から有名なスポットです。 平安時代より、その穏やかな風景と湖面に映る月は人々の心を和ませてきました。 周囲には茅葺き…(続きを読む)
東映太秦映画村

東映太秦映画村の中には、貴重な映画資料が数多く展示されています。特に映画文化館は、充実した資料を分かりやすく展示しており、歴史や映画製作に関する知識を身につけることが出来ます。 時代劇のオープンセッ…(続きを読む)
龍安寺

禅苑の名刹である大雲山竜安寺は、宝徳二年に足利将軍の管領職にあった細川勝元が徳大寺公の山荘を譲り受け妙心寺五代世の義天玄承(ぎてんげんしょう)を開山に向かえ創建しました。応仁の乱で焼失したのちも、勝元…(続きを読む)
渡月橋

渡月橋は、嵐山の大堰川に架かる橋で、平安時代初期の承和年間(834〜48年)に、空海の弟子にあたる道昌僧正が、現在の渡月橋の上流に架けられた葛野橋(法輪寺橋)が由来と言われています。渡月橋より下流は桂…(続きを読む)
鹿王院

右京区嵯峨北堀町。臨済宗の単立寺院。 足利義満が1379(康暦1)年に建立した宝幢禅寺(ほうどうぜんじ)鹿王院の開山塔院だったが、応仁の乱でこの建物だけが焼け残ったという。山門には義満の筆による「覚…(続きを読む)
淳和院跡

淳和院(じゅんないん)は右京四条二坊十一町〜十四町までの四町、南北516m、東西252mに擁された淳和天皇の離宮である。別名、西院とも呼ばれ、現在の地名のもととなっている。 淳和院は淳和天皇が皇太弟…(続きを読む)
梅宮大社

梅宮大社は古くから酒造と安産の神として信仰を集めている。社伝によれば、もとは相楽郡にあったが、嵯峨天皇の皇后、橘嘉智子(たちばなのかちこ)が現在地に移したと言われている。 神苑には、梅、桜、霧島つつ…(続きを読む)
左京区
京都府立植物園

京都府立植物園は大正13(1924)年に開園しましたが、第2次大戦中は食糧増産の場として利用され、戦後は連合軍に接収されて多くの樹木が伐採されるなどした時期もありました。昭和36(1961)年に再び公…(続きを読む)
京都府立 陶版名画の庭

地下鉄北山駅を下車して、すぐのところにあります。 安藤忠雄が設計した建物の中には「最後の晩餐」、「最後の審判」といった一度は見聞きしたことのある作品の実物大の陶版画が滝のように流れる水の隣で飾られて…(続きを読む)
琵琶湖疏水

京都市民のライフライン、琵琶湖疏水は日本人技師(田邉朔郎、当時21歳)が設計を行った初の大規模土木工事で、最初の着工は1885(明治18)年のことでした。 当初の灌漑、上水道などの目的だけでなく、日…(続きを読む)
知恩寺

百万遍の知恩寺さんといえば、「手作り市」。毎月15日にお堂の前で300-400店がにぎわいます。 京都の手作り市は作り手もお客さんもレベルが高いため、ここで自分の腕を試す若手デザイナーも多いと聞きま…(続きを読む)
吉田神社

吉田神社といえば節分祭。節分発祥の地としても有名ですが、全国の神を合祀した斎場所大元宮は、吉田兼倶が唯一神道(吉田神道)を大成した際に設けられ、国の重要文化財に指定されています。 八角形の独特の形を…(続きを読む)
赤山大明神

比叡山延暦寺の別院であり、888年に創建されました。円仁(慈覚大師)は入唐して大陸登州の赤山法華院に一時身をおき、帰朝して日本に赤山禅院の建立を思い立ちますが、志なかばで果たせず、遺言により弟子の安慧…(続きを読む)
下鴨神社

鴨川の支流、高野川と賀茂川が交わる三角地帯に位置し、京都で最も古い神社といわれる下鴨神社(正式名称:賀茂御祖神社)。崇神天皇七年(紀元前90年頃)に神社の瑞垣の修造がおこなわれたという記録もあり、平安…(続きを読む)
宝ヶ池公園

地下鉄松ヶ崎駅から国際会館駅の間に広がる宝ヶ池公園。 北部にある宝ヶ池は、江戸時代に農業用のため池として作られたもの。松ヶ崎側には大学ラグビーの対抗戦などが行われる運動公園、東部にはかつての京都競輪…(続きを読む)
詩仙堂

徳川譜代の臣で、大阪夏の陣で勇躍先登の巧名を立てた石川丈山が、戦にたずさわることをやめ、1641年に造営し没するまでの三十余年を過ごしたのがこの詩仙堂です。丈山は隷書、漢詩の大家で、また日本の煎茶の開…(続きを読む)
修学院離宮

後水尾上皇は1641(寛永18)年から離宮の候補地の選定を始めましたが、修学院離宮の場所に決定する迄、実に14年の歳月を要したといわれています。 現在離宮は上・中・下の御茶屋から構成されており、上御茶…(続きを読む)
高野川

京都、大原、三千院・・・。その大原の北部から水を集め、出町柳まで運んでいるのが高野川です。下鴨・高野付近の川沿いには桜が多く、春の美しい光景は多くの人々に喜ばれています。 しかし、昔は高野川が一度氾…(続きを読む)
曼殊院

最澄が比叡山に草創した東尾坊が明応4年に門跡寺院となり、平安後期から曼殊院と称されました。現在地には江戸初期の明暦2年に、桂離宮を造営した智仁親王の次男、良尚法親王が住持となったときに移され、境内の虎…(続きを読む)
糺の森

下鴨神社の境内に位置する糺の森は、かつては約495万平方メートル(約150万坪)の原生林であったが、中世の戦乱や明治4年の上知令によって、現在の約12万4千平方メートル(東京ドームの約3倍)の大きさと…(続きを読む)
八大神社

八大神社は今から約700年前の永仁2年に創建し、応仁の乱の兵火により焼失しましたが、慶長元年に再建されたものが現在の姿です。八大神社は祇園社(現 八坂神社)と同格で、皇居守護神12社中の1社として、東…(続きを読む)
出世稲荷神社

豊臣秀吉を一介の草履とりから天下人へ出世させたというゆかりの神社がこの出世稲荷神社です。秀吉は幼い頃から稲荷五社の神を信仰しており、松下嘉平治に仕えるころより、五柱の神の霊が一柱の大活神になって、自分…(続きを読む)
出町三角デルタ

京阪出町柳駅付近で高野川と賀茂川が合流し、三角州を形成して鴨川へと名前を変えます。その三角州、市民たちは親しみをこめて「デルタ」と呼び、晴れた日には多くの人々でにぎわっています。水辺で遊ぶ少年たち、の…(続きを読む)
北区
北山杉

京都駅から北西へ20キロ、京都市北区中川地域は古来より北山杉の産地として栄えてきました。京都御所に献上された北山杉は、桂離宮や修学院離宮といった皇室関連の建築物に多く用いられました。今でも中川地域には…(続きを読む)
光悦寺

元和元年に本阿弥光悦は、徳川家康から拝領した鷹ヶ峰の地に一族縁者や工芸職人とともに移り住み、芸術村を営みました。その折に、本阿弥家の先祖供養のため位牌堂をもうけたのがはじまりで、光悦の死後、ゆかりのこ…(続きを読む)
等持院

等持院は、暦応4(1341)年、足利尊氏が衣笠山の山頂にあった仁和寺の子院を譲り受け、この地に移築して等持寺の別院として中興、改宗し天龍寺の夢窓国師(むそうこくし)を開山としたのが始まり。 方丈と書…(続きを読む)
上賀茂神社

上賀茂神社は、賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)の通称です。この「別雷」とは「若雷」、つまり若々しい力に満ちた雷の神という意味だそうです。 さて、その上賀茂神社と南に位置する下鴨神社で5月15…(続きを読む)
大徳寺のイブキ

北区の大徳寺内にある仏殿の前に大きなイブキの木がある。 このイブキは、仏殿が寛文五(1665)年に再建されたため、その時に植栽されたものと言われている。イブキは、ヒノキ科ビャクシン属の高木で、日本で…(続きを読む)
源光庵

源光庵は、貞和2年に臨済宗大本山大徳寺の高僧、徹翁国師により隠居所として開創されましたが、後の元禄7年、曹洞宗復古道人の卍山道白禅師によって曹洞宗に改宗し、再興されました。 現在の本堂は元禄7年の創…(続きを読む)
今宮神社

上京区にある大将軍八神社が西の大将軍なら、北区にある今宮神社は北の大将軍に位置しています。大将軍とは方位をつかさどる神様の事です。 桓武天皇の平安遷都の始め、京都の町を守るために、京の四隅に『大将軍…(続きを読む)
常照寺

常照寺は、元和2(1616)年、日蓮宗中輿の祖といわれる日乾上人が、本阿弥光悦の土地寄進を受けて開創した鷹峰檀林(仏教の学問所)の旧跡で、旧山城六檀林の一つです。 学問寺である一方、寛永三名姑の一人…(続きを読む)
平野神社

平野神社は、延暦13(794)年、桓武天皇が平安遷都にあたり、大和国の四座の神を勧請したのが起こりです。平安遷都に際し、桓武天皇の生母、高野新笠姫を中心として大陸文化を導入したのが平安京の都造りに大い…(続きを読む)
上京区
北野天満宮

学問の神様としてあまりにも有名な、菅原道真を祀る神社。 京都内外を問わず、受験シーズンにお世話になった人も多いはず。 また、毎月25日に開かれる蚤の市にも多くの人々が訪れ、人々に「天神さん」の呼び名…(続きを読む)
大将軍八神社

一条通に面して立つ大将軍八神社は、うっかりしていると通り過ぎてしまうほどの小さな神社。しかし平安の昔には、内裏の西の守りを担っていたという由緒正しいお社です。 名前の由来となった大将軍とは、陰陽道に…(続きを読む)
梨木神社

京都御苑の東脇にある梨木(なしのき)神社は、 明治維新の功績者である三條実萬(さねつむ)・実美(さねとみ)父子を祀った神社で、三條家の旧邸が梨木町にあったことが名前の由来です。 実萬は江戸末期に三…(続きを読む)
織成館

織物と伝統の町、西陣。「織成館」(おりなすかん)はそんな西陣の魅力が詰まった織物のミュージアムです。西陣に多く見られる織屋建ちの建物内には、きらびやかな能衣装や全国各地の織物が常設され、予約をすれば工…(続きを読む)
御霊神社(上御霊神社)

地下鉄烏丸線鞍馬口駅徒歩3分、 烏丸通り上御霊前を東に入ると正面に見えてくる。 実は、御霊神社という名前の神社は日本各地に存在し、 京都市中京区、京都府福知山市、大阪市中央区、 神奈川県鎌倉市…(続きを読む)
相国寺

永徳2(1382)年、足利義満が建てた相国寺は、 正式には相国承天禅寺という臨済宗の禅寺。 本尊は釈迦如来。 京都五山の第二位に位し、 五山文学の中心となって多くの学僧を輩出したが、 相次ぐ…(続きを読む)
国会議事堂とどっちが古い? 京都府庁旧本館

国会議事堂は昭和11(1936)年に帝国議会議事堂として建設されました。 一方京都府庁は先に完成していた東京府庁舎などを参考に明治37(1904)年に建設されました。京都府庁は現在残っている府庁舎の…(続きを読む)
聚楽第址の石碑

これは聚楽第跡の石碑です。大正時代に立てられましたが、2008年3月からは写真にある中立売裏門通りの場所に移動しています。 また、最新の発掘調査に基づく推定範囲でこの場所は聚楽第本丸西堀にあたる事が…(続きを読む)
平安宮大蔵省跡

大蔵省は今制八省の一つで、多くの倉庫があった大蔵を合わせて平安宮の北八町を占めていた。出納・収納・度重衡などを職務とし、諸国から貢進される調庸・銭などの貢献物を、正倉などの倉庫に納め、官人給与の禄やさ…(続きを読む)
一条戻橋

安部清明を祀る清明神社から少し南にある一条戻橋。 一見どこにでもあるこの橋には古くから様々な伝説が残っています。 霊界とつながっているとされたこの橋の上で、 女の姿を借りた鬼が現れたという話が平…(続きを読む)
白峯神社

コトブキ時計店から今出川通を西へ歩くと、白峯神社の大きな門が見えてきます。 白峯神社は平安時代の蹴鞠の名手であった飛鳥井家の邸宅後に立つ神社で、今ではサッカーをはじめとする様々なスポーツにご利益があ…(続きを読む)
中京区
女紅場跡

鴨川にかかる丸太町橋の西詰めに、ひときわ目を引く洋風の建物があります。現在はレストランになっていますが、大正時代の電話局の建物だそうです。 さらに近くに足を運ぶと、建物の脇に「女紅場(にょこうば)址…(続きを読む)
八木邸

八木家は室町時代に壬生村に居を構え、村の経営や壬生狂言に携わり代々、村の行司役を勤めていました。また壬生村と京都守護職や所司代とも深い関わりがあり、中心的立場を担う有力郷士でした。 幕末、八木家11…(続きを読む)
高瀬川一之船入

高瀬川は慶長16(1611)年頃、角倉了以が開いた運河でここを通行する高瀬舟の荷物のあげおろしをする船溜所を船入といい、川の西方の堀割を一之船入といいます。 角倉氏は京都の中心部に物資を運びいれるた…(続きを読む)
京都文化博物館

京都文化博物館は京都の文化とその歴史を紹介し、また新たな文化の創造力を生み出すために作られた文化施設です。 別館は重要文化財に指定されている旧日本銀行京都支店であり、お洒落な三条通のイメージをよりい…(続きを読む)
高瀬川

プラスワン河原町御池店のすぐ東には、有名な高瀬川が流れています。ふと目をやると、橋のそばに「此(この)付近加賀藩邸跡」の立て札。実は、この高瀬川の西側から河原町までのところには、江戸時代に加賀藩の藩邸…(続きを読む)
錦天満宮

錦天満宮は、新京極通りと錦市場の交わる、ちょうど四条河原町のど真ん中に位置する。 京都で最も栄える繁華街に、伝統的・文化的な神社が調和するその姿は「一見の価値アリ」という訳で、通年を通して参拝客で賑…(続きを読む)
分銅屋

分銅屋は、江戸時代初期創業の足袋の老舗。品質の良さで、この店の足袋を愛用している役者や狂言役者は多数。白足袋のほか、京友禅の足袋などもあるそう。 ただ、このお店は足袋の専門店としてだけではなく、三条…(続きを読む)
家邊徳時計店

家邊徳時計店は、1890(明治23)年に建築(木骨レンガ造り2階建て)された洋風商業建築。 京都に現存する民間洋風商業建築としては最古の部類に属し、内部には金庫室や螺旋階段があり、1階は三連アーチ窓…(続きを読む)
平安京創生館

■平安京創生館 延暦13(794)年、桓武天皇によって平安京は建設されました。 碁盤の目状の町並みからなる美しさは圧巻で、現在の京都でもそれを感じることは十分可能です。その平安京の様々な魅力を感じ…(続きを読む)
高松神明神社

姉小路通釜座東入った北側に高松神明社があります。この付近は醍醐天皇の皇子・源高明の邸宅でした。その後、平安時代後期には後白河天皇の内裏となります。 1156年の保元の乱では、崇徳上皇方の白河北殿に対…(続きを読む)
総本山誓願寺

四条河原町のROUND1、その北西に位置する総本山誓願寺。 もともとは奈良の近鉄「尼ヶ辻」駅付近にあったが、平安遷都とともに京都(現・上京区元誓願寺通小川西入る)に移転、さらに豊臣秀吉の命令により現…(続きを読む)
大西清右衛門美術館

大西清右衛門とは千家十職の釜師で、大西家は室町時代後期から400年以上続く京釜師の家。現在は16代清右衛門が当主。 京都市中京区の三条釜座に工房があり、大西清右衛門美術館も併設され、この美術館では代…(続きを読む)
旧前川邸

1863年から2年間、新選組の屯所となった建物。 上洛する浪士組(後の新選組)の宿舎を選定するにあたり、市中情勢にも詳しく役人からの信頼も厚い前川本家がその仕事を任された。 前川本家では、壬生の地が…(続きを読む)
京都三条会商店街

東西を貫く三条通りの堀川通りから千本通りの間、 全長約800mの商店街。 アーケードの下365日晴れの街として日々賑いを見せ、 総店舗数は約180店舗と探しもの何でもそろう。 午後2時〜9時ま…(続きを読む)
本能寺はここにあり。本能寺跡

あの有名な本能寺の変の頃、本能寺は四条西洞院、油小路・小角・錦小路に渡る地域にありました。本能寺の変後、豊臣秀吉によって現在の場所(寺町御池)に移転されました。 現在では京都市立堀川高等学校本能学舎…(続きを読む)
先斗町

祇園とともに京都の花街を代表する「先斗町(ぽんとちょう)」。 大通りとは全く違う京都の表情を味わう事ができるこの通りはまた、昼と夜ではガラリと印象が変わるのも特徴的です。その独特な名前の由来はポルト…(続きを読む)
八坂神社御供社

京都三条会商店街の一角、 三条通黒門に八坂神社御供社(ごくうしゃ)が立つ。 その設立は、896年、平安京を原因不明の疫病が襲ったことに遡る。当時、疫病は疫神や怨霊の仕業と考えられ、これを鎮めるため…(続きを読む)
神泉苑

御池通りの名前の由来とも言われる神泉苑。 平安京の建都の際、天皇の住む大内裏の南に広がる湿地帯を利用して作られました。当初は東西200m、南北400mの敷地で、天皇の遊興の場であるとともに、風水的に…(続きを読む)
壬生寺

ここは律宗の寺院であり、三井寺の僧が本尊として地蔵菩薩立像(重要文化財)を安置し、堂を立てたのに始まります。正安2(1300)年に円覚上人が創始した仏の教えを身振り手振りの無言劇に仕組んだ壬生大念仏狂…(続きを読む)
京都電電ビル西館(旧京都中央郵便局)

三条烏丸に位置する新風館という若者向け専門店商業施設は、その昔、逓信省の京都中央電話局として、逓信省技師吉田哲郎の設計、清水組の施工により建設されました。 日本における近代建築のパイオニアである吉田…(続きを読む)
本能寺

本能寺は応永22年に日隆上人により創建された、法華宗本門流の大本山です。 天正10年、明智光秀が織田信長を攻め、自害させた「本能寺の変」で知られ、「本能寺の変」当時は四条西洞院のあたりにあったが、焼…(続きを読む)
梛神社

中京区四条千本にある梛神社は、京の悪疫退治のため祭神を東山八坂に祭る前、いったんこの地の梛の森に神霊を仮祭祀したのが起こりとされている。そのため別名として元祇園社とも呼ばれている。 また、境内には式…(続きを読む)
京都万華鏡ミュージアム

世界各国の万華鏡を収蔵し、その中から常時50点程を展示しています。高価な万華鏡でも直接手に取り自由に動かして見ることが出来ます。 また、毎月各種のイベントや手作り教室等も開催されています。光と鏡が織…(続きを読む)
六角堂

中京区烏丸通り六角を東に入ってスグの北側に位置し、本堂が六角宝形造であることから、一般に「六角堂」と言われ、地元京都では「六角さん」との愛称で親しまれる。西暦587年、聖徳太子を開基として創建されたと…(続きを読む)
下京区
天道神社

天道神社は、延暦13年(794)、桓武天皇が都を平安京に遷都のとき、もともと長岡京に鎮座されていた天道神社を万民豊穣、子孫繁栄、悪疫退散を祈願され、三条坊院東洞院(現在の東洞院御池上る付近)の地に勧請…(続きを読む)
冠者殿社

八坂神社の境外末社で御祭神は八坂神社と同じですが、ここは本社で祭る神霊の穏やかなはたらきの和魂と対をなす猛々しいはたらきの荒魂を祭っています。 毎年十月二十日に「誓文払い」と呼ばれるお祭りがあります…(続きを読む)
シューズダストボックス

さて、問題です。京都市では靴は何ごみでしょうか? 答えは家庭ゴミ。でも靴のヒールやソールには燃えない素材や金属が使われています。ジェイアール京都伊勢丹では2Fの婦人靴売り場の一角にシューズダストボッ…(続きを読む)
管大臣神社

仏光寺通り新町を西に入ったところにある神社。 菅原道真(845〜903)の紅・白梅殿という邸宅や 菅家廊下と称する学問所の跡がある。 道真誕生の地ともいわれ、 境内には産湯の井戸が保存されてい…(続きを読む)
京都タワー

京都駅を出ると真っ先に視界に飛び込んでくる京都のランドマーク。 その独特の形は海のない京都を照らす灯台をイメージしているとか。 1Fは京都の名産品がそろう名店街が、地下3階には大浴場まであります。…(続きを読む)
京都市学校歴史博物館

御幸町通仏光寺を下ったところに位置する京都市学校歴史博物館は、日本で最初の学区制小学校である番組小学校を中心に、京都の教育と学校の歴史を、教科書、教具・教材や古文書などの歴史資料を基に展示している。 …(続きを読む)
西京区
松尾大社

太古の昔よりこの地方一帯に住んでいた住民が、松尾山の山霊を頂上に近い大杉谷の上部の磐座(いわくら)に大山咋神を祀って、生活の守護神として尊崇したのがはじまりといわれています。渡来人の秦氏が氏族の守護神…(続きを読む)
華厳寺

妙徳山・華厳寺は江戸時代中期の享保8年、華厳宗の再興のために鳳潭上人(ほうたんしょうにん)によって開かれ、現在は臨済宗に属する禅寺です。本尊は大日如来でそのほかに地蔵菩薩も安置しており、全国から地蔵信…(続きを読む)
月読神社

京都市西部を嵐山から南下する桂川の右岸、阪急嵐山線・松尾駅の南西約500mの松尾山山麓に鎮座する。松尾駅の真西にある松尾大社の大鳥居前を左折・南下して約10分。 延喜式神名帳の山城国葛野郡にある名神…(続きを読む)
樫原廃寺跡

樫原廃寺跡(かたぎはらはいじあと)は、西京区樫原にある古代寺院跡で、国指定の史跡である。1967年に行われた発掘調査により八角塔と中門の遺構が検 出され、四天王寺式の伽藍配置であったと推定された。19…(続きを読む)
西芳寺

苔寺の名で有名な西芳寺は、今から約1250年前の天平年間に行基が開山し、後の暦応2年に夢窓疎石が庭を造り、臨済宗の西芳寺として復興したといわれています。 当時は現在のような苔は生えていませんでしたが…(続きを読む)
地蔵院

竹の寺と呼ばれる地蔵院は、臨済宗の寺で一休禅師が幼少の頃、修養された寺でもある。孟宗竹や真竹が美しい林をなしている。貞治6年(1367)、細川頼之が創建し、かつては大寺院であったが、応仁の乱で諸堂を焼…(続きを読む)
浄住寺

西芳寺の南、紅葉や桜が生い茂る自然石の長い石段の奥に、荒廃はしているが竹林を背にした閑寂な寺が立つ。平安時代に慈覚大師によって開かれた古刹で、まさに古寺といった感じが漂う。 本堂は黄檗宗の特色を兼ね…(続きを読む)
東山区
高山彦九郎像(土下座像)

京阪三条店のすぐそばにあるのは、待ち合わせスポットとして有名な高山彦九郎像。地元の人からは、その姿から土下座像と呼ばれています。 高山彦九郎は江戸時代後期の有名な尊王思想家で、三条大橋から京都へ入る…(続きを読む)
八坂の塔

東山のシンボル八坂の塔は、またの名を臨済宗建仁寺派の寺院、法観寺の五重の塔といいます。この地はかつて渡来氏族の八坂氏が住んだ土地であると言われており、八坂という地名はこれに由来しているようです。 法…(続きを読む)
豊国神社

豊臣秀吉を祀っている神社で、一般に「ホウコクさん」の愛称で人々に親しまれています。慶長3(1598)年に63歳で亡くなった秀吉の遺体は、もとは阿弥陀ヶ峯の中腹に葬られていましたが、豊臣家滅亡後、徳川に…(続きを読む)
山科区
元慶寺

元慶寺は僧正遍昭によって元慶元年(877)に建立され、本尊は薬師如来です。寛和2(986)年、花山天皇がこの寺で出家、花山法皇と称したこともあり花山寺とも呼ばれています。その後、多くの寺領で栄えたが応…(続きを読む)
随心院

山科区の小野付近は、遣隋使で有名な小野妹子とつながりのある小野一族の勢力が強かった土地で、随心院は小野小町ゆかりの寺として知られています。 境内では小町が朝夕の化粧に使ったとされる井戸の跡や、多くの…(続きを読む)
勧修寺

勧修寺は約1100年前の昌泰3(900)年、醍醐天皇が生母藤原胤子のため建立したものと伝えられています。その後文明2(1470)年、兵火で焼失して衰退したが、江戸時代に入って再興されました。見所は、平…(続きを読む)
天智天皇山科陵

天智天皇陵は御廟野古墳とも呼ばれ、山科盆地北辺の南向きの傾斜面に位置する終末期古墳です。古墳の後ろには琵琶湖疏水が流れ、参道脇には天智天皇が日本ではじめて時計を設置したことにちなんで日時計が設置されて…(続きを読む)
南区
羅城門跡

九条通りと壬生通りの交差点を西に歩いていると、 通りの北側の小さな児童公園の中にひとつの石碑が立っている。 ここはその昔、平安京を貫く朱雀[すざく]大路の正門として、 794年の平安遷都の際に建…(続きを読む)
東寺

東寺(正式名称:教王護国寺)は平安建都の際、都の南玄関、羅城門の東に作られた。 国宝の五重塔は、高さ57メートルの日本最高の塔で、寛永20(1643)年に、徳川家光が再建奉納したもの。また、重要文化…(続きを読む)
伏見区
寺田屋

江戸初期から続く船宿。 この宿では歴史上有名な二つの事件が起きている。 文久2(1862)年4月、薩摩藩の尊王攘夷派と公武合体派が乱闘、 9人の尊い犠牲者を出した。 これを薩藩九烈士といい維新…(続きを読む)
醍醐天皇後山科陵

醍醐天皇後山科陵は、醍醐天皇のお墓です。 平安時代中期の西暦897年に即位した醍醐天皇は、紀貫之らに「古今和歌集」の撰進を命じたことなどで知られています。 その治世は34年にわたり、摂政や関白を置…(続きを読む)
京都の出入り口、六地蔵めぐり 大善寺

まだまだ暑い8月22日、23日に京都では六地蔵めぐりなる伝統行事が行われます。 京都につながる6本の旧街道の沿いに祀られた6体のお地蔵さまを回り、お札をもらいます。6つ揃ったお札を玄関先につるすこと…(続きを読む)
鳥羽離宮跡

鳥羽離宮とは、白河天皇が創建した譲位後の御所。現在の京都市南区上鳥羽、伏見区竹田、中島、下鳥羽の一帯に位置し、鳥羽上皇の代にほぼ完成した後は、14世紀頃まで代々院御所として使用された。約180万平方メ…(続きを読む)
伏見港公園

伏見港は秀吉の伏見城築城の際に作られ、大坂との水運の拠点となりました。 しかし、陸上交通の近代化により、舟運が衰退し、昭和30年代半ばには港としての機能は幕を閉じました。 その跡地は公園となり、地…(続きを読む)
西岸寺

「歎異抄」で有名な親鸞。浄土真宗の開祖ですが、その親鸞に奥さんがいたことをご存知でしたか? 京阪藤森駅のやや南東、深草商店街の中にある西岸寺は、親鸞とその奥さんの「玉日姫」にゆかりのあるお寺です。 …(続きを読む)
大手筋

近鉄桃山御陵前駅でにぎわいを見せているのが、洋服の病院・大手筋店のある大手筋商店街である。 この商店街は、アーケードを中心に約400メートル程続く道に、多種多様なお店がひしめき合っている。 「大手…(続きを読む)

![京eco2Ring[みやこエコツーリング]](https://www.moppen-kyoto.com/wp-content/themes/main/images/eco2_title.png)